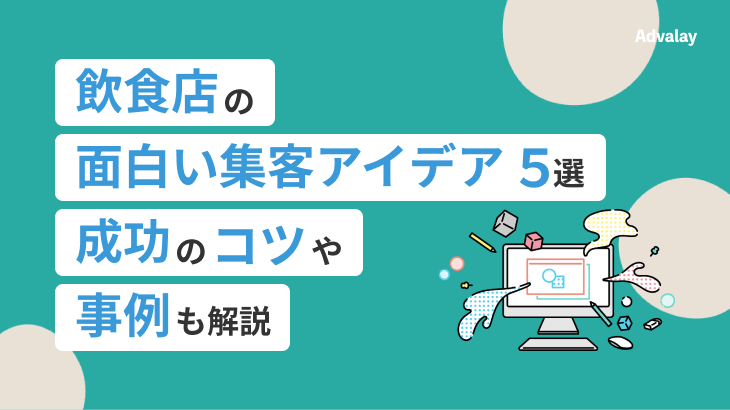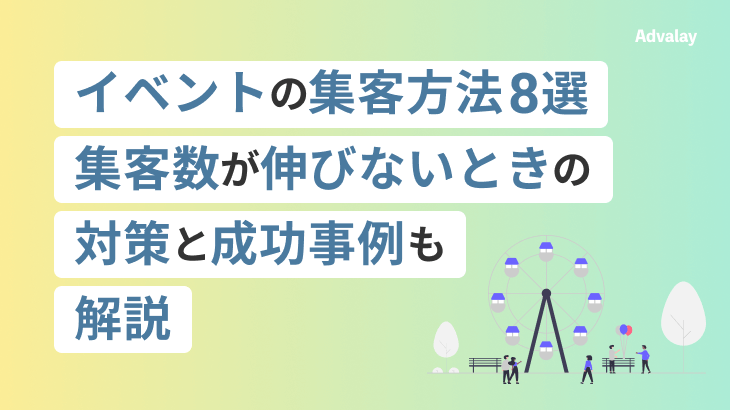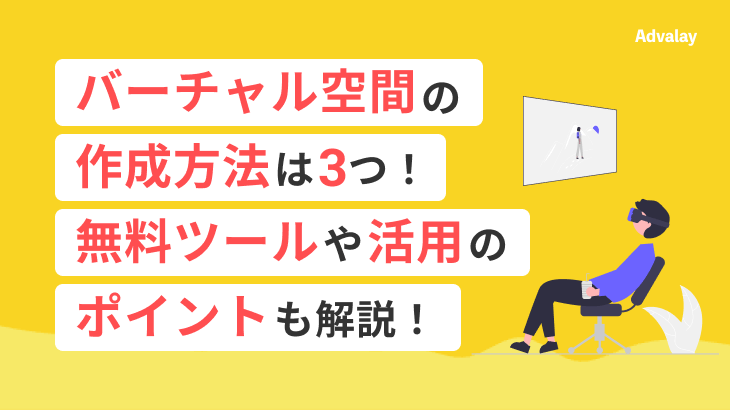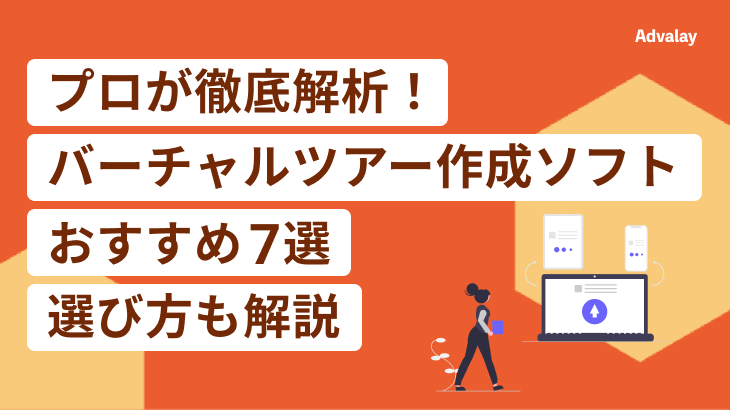3DVRで作るオンラインツアー!メリットや活用・制作方法までご紹介
「コロナ禍で、来場者が減って困っている」
「オンラインツアー導入したいけれど、どのように活用すればいいの?」
「オンラインツアーを製作してみたいけれど、作り方やツールがわからない…」
こんなお悩みはありませんか?
オンラインツアーはコロナ禍をきっかけに、お家で楽しめる新時代のツアーとして注目を集めいています。
本記事では、最新鋭のデジタル技術「Matterport」で制作するオンラインツアーの概要やメリット、制作方法まで徹底解説します。
私たちは、Matterportの事業をメインに行っており、美術館や博物館などの大規模施設のオンラインツアーを製作した実績があります。
ぜひ、以下の記事を読みすすめていただき、オンラインツアーの特徴や魅力を知っていただけますと幸いです。
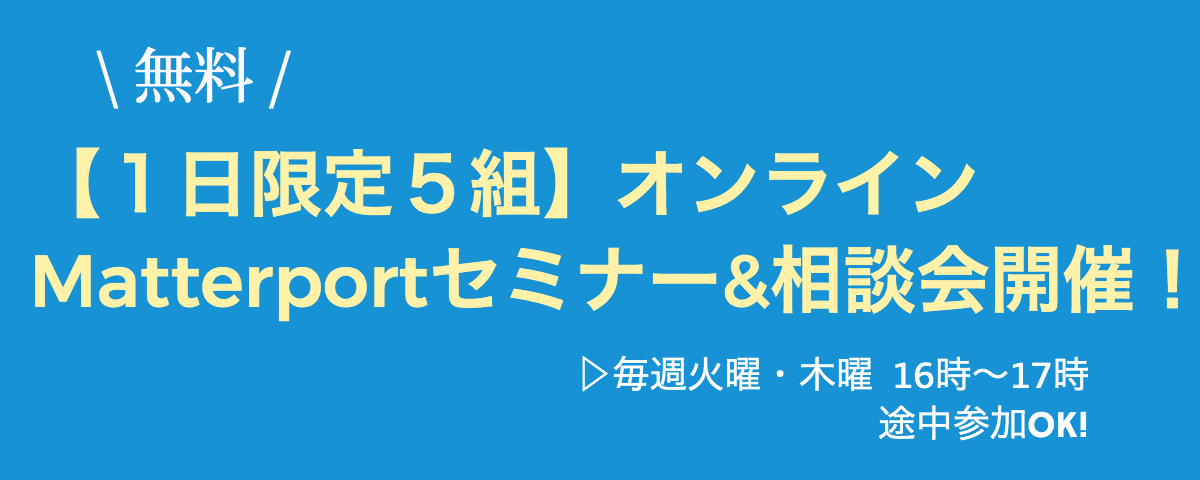
オンラインツアーとは?
直接現地に行かずとも、オンラインで気軽に旅行気分を楽しむことができる旅行の疑似体験サービスです。
これまで、時間や場所、費用面などさまざまな制約により、旅行することを諦めていた方も多いのではないでしょうか。オンラインツアーは、24時間365日いつでも自宅から簡単に参加できます。
時間、場所を選ばずとも、世界中の景色や文化やその地域独自の色に触れられるサービスとして、多方面での活用が期待されています。

オンラインツアーは、動画配信サービスを活用して行われるものが多いです。具体的には、現地のガイドさんや旅行会社さんが観光地現地でカメラを回し、そこから配信される映像をリアルタイムで家から視聴するというものです。
動画配信サービスを活用したオンランツアーも双方向のコミュニケーションを可能にしてくれるサービスとして非常に魅力的ですが、今回は動画配信とは最新鋭技術「マーターポート(Matterport)」というサービスを使ったオンラインツアーについてご紹介していきます。空間を3Dモデルで表現できるとてもおもしろいサービスで、他とは少し違ったツアーを実現することができます。
観光産業では、2023年の訪日外国人旅行者数が過去最高を記録するなど回復の兆しを見せていますが、地方の観光地や中小規模の施設では依然として集客に苦戦しているケースも少なくありません。オンラインツアーは、そういった施設にとって新たな顧客接点を生み出し、実際の来場につなげるための重要な施策として注目されています。
オンラインツアーの実施方法は大きく分けて以下の3種類があります。
- ライブ配信型: ガイドが実際に現地を歩きながらリアルタイムで解説するスタイル
- 録画型: あらかじめ撮影した動画コンテンツを配信するスタイル
- 3D空間型: Matterportなどの技術を使って空間を3Dで再現し、ユーザーが自由に探索できるスタイル
それぞれに特徴がありますが、3D空間型の最大の利点は「ユーザー自身が主体的に空間を探索できる」点にあります。受動的に視聴するだけでなく、自分の興味に合わせて見たい場所を自由に選べるため、没入感と満足度が高まりやすいのが特徴です。
オンラインツアーを制作できるMatterportとは?
オンラインツアーの制作には「Matterport(マーターポート)」というデジタル技術を使います。
Matterportとは、360度カメラを利用して空間を撮影し、その空間を3Dの模型データで作成するサービスです。
映像クオリティーや費用対効果の高さから、さまざまな業界で導入が進んでおり、観光・エンタメ業界でも多数の活用事例があります。
Matterportの詳しい解説は下の記事にも記載していますので参考にしてみてください。

Matterportの歴史と技術的背景
Matterportは2011年にアメリカで設立され、当初は不動産業界向けのバーチャルツアー技術として開発されました。不動産物件の内見を効率化するツールとして急速に普及し、その後、観光、教育、小売りなど様々な業界へと活用の場を広げています。
日本では2018年頃から徐々に認知が広がり始め、コロナ禍を機に爆発的に需要が高まりました。特に美術館や博物館など文化施設での導入が進み、「新しい観光」のカタチとして定着しつつあります。
Matterportで使用する機材
Matterportでの撮影には主に次の機材が使用されます。
- 専用3Dカメラ: Matterport Pro2 3Dカメラなどの専用機材
- 360度カメラ: RICOH THETA Z1やInsta360など
- スマートフォン: iPhone 12以降や一部のAndroid端末では専用アプリで撮影可能
撮影精度や品質は使用する機材によって異なりますが、プロフェッショナルな用途では専用の3Dカメラを使用するのが一般的です。高精細な空間データを取得できるため、より没入感のある体験を提供できます。
Matterportでつくるオンラインツアー5つの特徴
Matterportで制作したオンラインツアーには次のような特徴があります。
- 4K高画質のウォークスルー映像
- 施設内のハイライトを自動再生
- 施設や展示の説明情報を掲載
- 3Dの立体模型と平面フロアマップで簡単移動
- 地域をまるごとPR
以上の5つについて詳しく見ていきましょう。
1.4K高画質のウォークスルー映像

まず一つ目の特徴は、マーターポートのデータは4Kを使った高画質で表示されるため本物同様の3Dモデルができあがります。そのため、観光地の細部までデータ上にうつしだすことができ、ストレスなくオンラインツアーを楽しむことができます。
高解像度のテクスチャマッピングにより、絵画の筆致や彫刻の細かい質感、歴史的建造物の装飾など、芸術作品や文化財の細部まで忠実に再現されます。実際の訪問では見落としがちな細部も、オンラインツアーではじっくりと観察することができるため、教育機関や研究者からも高い評価を得ています。
また、照明条件によって見え方が変わる展示物も、最適な照明環境で撮影することで、実際の訪問では見られない理想的な状態で鑑賞することが可能です。美術館の監修者と連携し、作品の意図を最も適切に伝える環境を構築できる点も大きなメリットです。
2.施設内のハイライトを自動再生
マーターポートデータには、「ハイライト」と呼ばれる特定のポイントをピックアップして掲載できる機能があります(画面下部の、帯状に写真が連なっているところ)。このハイライト写真は、順番に自動再生することができるため、何も操作せずとも施設内の魅力的なコンテンツや空間をダイジェストで届けることができます。
マーターポートは、「見たい場所」を自由に自分の手でコントロールして見ることができるというのも大きな魅力の一つですが、それに加えて、自動で「魅せたい場所」をアピールできると施設の良さを漏れなく届けることができます。
ハイライト機能は特に初めてMatterportを体験するユーザーにとって重要な要素です。ユーザーは3D空間内での移動操作に慣れていないことが多く、最初から自由探索を求められると戸惑う場合があります。そこでハイライトツアーを最初に体験してもらうことで、操作に慣れながら主要なポイントを効率よく巡ることができます。
企業や施設側にとっても、マーケティングの観点から重要なポイントを確実に訪問者に見せられるため、情報発信の効率が高まります。例えば、博物館では目玉展示を必ず見てもらえるようにハイライトを設定したり、商業施設では特別なキャンペーン商品がある売り場を優先的に案内したりといった戦略的な活用が可能です。
3.施設や展示の説明情報を掲載
3つ目は、マーターポートの大きな魅力である「タグ」と呼ばれる機能です(下の画像:吹き出しの先っぽ丸ポチ)。このタグ機能は、データ内に写真・動画・PDF・GIFなどのコンテンツを追加で埋め込むことができるというものです。空間データだけでは伝えづらい情報を、文字や動画を使って補足することができます。

リアルでは、時間の制約や人員不足などにより全てのお客様に専門的な情報を伝えることが難しい場面もあると思います。それに対して3Dデータの場合、一度コンテンツを作成してしまえばデータを見に来た全てのお客様に対して観光地の特徴や魅力を届けることができるため、お客様のツアーに対する充実度も高まります。
うまくタグを活用している事例です。
タグ機能の活用方法は多岐にわたります。
- 多言語対応: 同じ展示に対して複数言語の解説を追加することで、国際的な訪問者への対応が可能
- 追加コンテンツの提供: 展示物の制作過程や裏話などの補足情報を動画で紹介
- 季節変化の表現: 四季折々の風景写真を同じ場所に複数タグとして配置し、季節による変化を表現
- インタラクティブ要素: クイズやゲーム要素を埋め込み、エンゲージメントを高める
- 関連商品へのリンク: 美術館の展示品に関連するミュージアムショップ商品へのリンク設置
特に教育現場での活用では、展示に関する深堀り情報や学習指導要領に沿った解説を埋め込むことで、社会科見学や修学旅行の事前・事後学習教材として効果的に活用できます。また文化財の保存・記録の観点からも、修復前後の状態比較や、時代による変遷を示す資料をタグとして埋め込むことで、学術的な価値を高めることが可能です。

4.3Dの立体模型と平面フロアマップで簡単移動
マーターポートで作成されたデータは、「平面図」「立体図」「空間移動」の3つの視点で見ることができます。そのためオンラインツアー中、自分が今どこにいるのか、常に観光地の全体を把握しながら観光を楽しむことができます。


地図を見ながら自分が行きたい観光地を巡ることができるのは、まさにリアルでの旅行の疑似体験と言えます。この「地図を利用しながら旅行する」という点は、オンライン、オフラインともに共通しているのに対して、瞬間的に「行きたい場所」まで飛べるのはオンラインだけが持っている魅力です。
Matterportの視点切り替え機能は、空間認知を助ける重要なツールです。人間は新しい場所を訪れると、通常その空間構造を把握するのに時間がかかりますが、Matterportでは即座に全体像を理解できます。
この機能は特に以下のような施設で効果を発揮します:
- 大規模美術館・博物館: 複数フロアや多数の展示室がある施設での迷子防止
- 迷路のような構造を持つ歴史的建造物: 城郭や寺院など複雑な構造を持つ建物の全体像把握
- 広大な敷地を持つ施設: テーマパークや動物園など、広範囲にわたる施設の効率的な移動計画
実際のユーザー調査によると、平面図と立体図の両方を活用できる環境では、ユーザーの滞在時間が約1.5倍長くなる傾向があります。これは空間を理解しやすくなることで探索意欲が高まり、より多くのコンテンツにアクセスするためと考えられています。
5.地域をまるごとPR
マーターポートの撮影は、博物館や美術館程度の規模であれば1〜2日で撮影することができます。そのため、その地域内にある観光地を複数撮影し、地域丸ごと PRすることができます。同地域の施設や観光地同士で連携し、ゲーム性のあるコンテンツやイベントの企画などを通してオンラインツアーを盛り上げていくことができれば面白いツアーになるのではないでしょうか。
地域全体をつなげたオンラインツアーの具体的な活用アイデアとしては:
- デジタルスタンプラリー: 各施設のMatterportモデル内に隠されたQRコードやキーワードを集めるゲーム
- 地域ストーリーツーリズム: 地域の歴史や文化をストーリーラインとして各施設を結びつける物語体験
- 季節限定バーチャルイベント: 夏祭りや冬の雪灯籠など、季節のイベントを3D空間内で再現
- 地域特産品巡り: 食や工芸品など地域特産品の製造現場や販売店を結んだ産業観光ツアー
これらを複合的に組み合わせることで、オンラインだけでなくリアル来訪者の周遊促進にもつながります。例えば、長野県の小布施町では、葛飾北斎館を中心に町内の複数の文化施設や店舗をMatterportで撮影し、「小布施まるごとミュージアム」としてデジタルとリアルを融合させた観光促進を実現しています。
地域全体のデジタル化は、DMO(観光地域づくり法人)や自治体が主導するケースが増えており、地方創生交付金や観光庁の補助金を活用した事業として取り組まれることも多くなっています。
愛知県蒲郡(がまごおり)市のオンラインツアー事例
愛知県蒲郡市では、Matterportのオンラインツアーを活用して、市全体の地域活性化を実現しています。
蒲郡にある次の5つの施設の撮影データをまとめて掲載することで、施設単体でPRするよりもそれぞれの施設が持つ魅力を生かした相乗効果を期待できます。
生命の海科学館

生命の海科学館は、蒲郡市でも有名な科学館で、さまざまな貴重なコンテンツが展示されています。
YouTubeでも、展示の解説動画を配信されていたため、更に多くの人に見てもらえるようMatterport映像内にもコンテンツを挿入しました。
時間や周囲の観光客を機にすることなく、無人の博物館を独り占めできるので、科学館好きにはたまらない空間ではないでしょうか。
蒲郡クラシックホテル

蒲郡クラシックホテルは歴史のあるホテルで、風情豊かな建物が特徴的です。
通常のホテルよりも少し宿泊費用が高額ですが、記念日など特別な日に若年層にも利用してほしいとの思いでMatterport化しました。
こだわりの内装もMatterportの4K映像で繊細に表現されており、ユーザーの興味をひきつける映像に仕上がっています。
六角堂

六角堂は、蒲郡クラシックホテルと同じ敷地内にあるレストランです。
建物の構造が六角形という珍しい形をしていますが、現地では真上の視点から建物を見られないため、六角形を認識できません。
そこで建物をMatterport化することで、Matterportの「立体図」視点で映像をみると、綺麗に六角形が確認できます。
通常は見られない景色やコンテンツを楽しめるのもオンラインツアーの大きな魅力と言えます。
竹島水族館|インタラクティブな海洋生物体験
蒲郡市の人気スポットである竹島水族館も、Matterportを活用したオンラインツアーを導入しています。実際の水族館では動き回る魚たちを撮影するのは困難ですが、オンラインツアーでは水槽ごとに代表的な魚の詳細情報や動画コンテンツを埋め込むことで、より教育的な体験を提供しています。
特に人気の飼育員による「餌やりタイム」の様子を動画で埋め込むことで、現地でしか見られない特別なイベントの雰囲気も伝えることができます。また、生態や保全活動に関する詳細情報も提供することで、単なる観光だけでなく環境教育としての価値も高めています。
形原温泉|季節の魅力を伝える仕掛け
蒲郡市の形原温泉では、四季折々の魅力を伝えるためのユニークな取り組みを行っています。温泉街全体のMatterportツアーに、春の桜、夏の海水浴、秋の紅葉、冬の雪景色といった季節ごとの風景写真をタグとして埋め込み、一年を通じた温泉街の魅力を伝えています。
また、宿泊施設の客室や温泉、食事処なども詳細に撮影することで、旅行前の「下見」としての機能も果たしています。実際の予約サイトとも連携させることで、気に入った客室を見つけたらすぐに予約できるシステムを構築し、オンラインからリアル来訪への導線を強化しています。
オンラインツアー活用方法5選
オンラインツアーをどのような場面で活用できるか、5つの方法を紹介します。
- 予習ツアーで旅のきっかけ作り
- ECサイトと連携しお土産やグッズを販売
- コンテンツの一部を有料化
- 動画配信を併用したライブ配信ツアー
- 教育・研修の教材
- バリアフリーツーリズムの推進
- 災害復興・文化財保存の記録
①予習ツアーで旅のきっかけ作り
MatterportのオンラインツアーをWebサイトやSNSに掲載しておき、現地の訪問する前に閲覧してもらうことで「予習ツアー」として活用できます。
観光地の特徴や魅力、現地ならではの醍醐味を事前に知ってもらうことで、現地に訪れた際「予習の答え合わせ」を楽しんでもらえます。
「ここ〜が有名なところだ!」「この建物って◯年前に〜が作ったらしいよ!」など事前に豆知識を持っておけば、観光中の会話も盛り上がるのではないでしょうか。
Matterportは、観光地をリアルに疑似体験してもらえるため、ユーザーの「行きたい欲」を引き出し、旅のきっかけづくりに適しています。
②ECサイトと連携し、お土産やグッズを販売
Matterport映像の中に、ECサイトのリンクを埋め込み、お土産や施設オリジナルのグッズを販売するのも良いでしょう。
ECサイトだけでは、ショッピングの「ワクワク感」「臨場感」に欠けるため、買い物に楽しみを求める方は満足できないことも多いものです。
そこでオンラインツアーの臨場感や世界観をの楽しみながら、商品を見ることで、購買意欲も高くなることが予想されます。
複数サイトを移動することなく、Matterportデータ一つで買い物まで完結できるので、ユーザーに負担をかけることなくオンラインショッピングを楽しんでもらえます。
③コンテンツの一部を有料化
Matterport内のコンテンツの一部を有料化することで、オンラインツアーの新たなビジネスモデルを確立できます。
Matterportデータは基本的に無料で閲覧できますが、データ閲覧自体を有料にする、またはタグなど特定のコンテンツの閲覧権限を有料で販売する仕組みを構築できます。
美術館や博物館のレアな展示や、オリジナルの音声コンテンツは価値が高いため、有料販売することでコアなファンは応援の意味も込めて購入してくれる可能性が高いです。
オンラインでは収益化がむずかしいと考える方も珍しくありませんが、工夫一つでオンラインならではのマネタイズポイントを設置できます。
④動画配信を併用したライブ配信ツアー
Matterportデータを、ZOOMやライブ配信などリアルタイムで配信できるツールと連携することで新たな活用を期待できます。
Matterportでつくるオンラインツアーの唯一のデメリットは、リアルタイムで施設を見られないことです。
博物館の学芸員やスタッフが、Matterportデータを動かしながら施設や展示の説明をする様子をライブで配信することで、リアルタイムのツアーを実施できます。
オンラインであれば、質問もしやすいため、現地のツアーよりもより展示に詳しくなれる可能性もあるでしょう。また、施設側、ユーザー側ともにコストをかけることなくツアーに参加できることもメリットの一つです。
⑤教育・研修の教材
Matterportデータは教育コンテンツとしても活用できます。
教育教材として利用する場合は、編集時にクイズ機能や音声、案内ガイドなどを搭載し、楽しく学べる仕組みを作ります。
小学校や教育施設で、行政施設や工場のオンラインツアーを公開することで、現地に行かずとも社会科見学を実施できます。
移動コストもかからないため、小さい子供でも楽に施設を見学できるため、今後学校での導入が進むと予想されます。
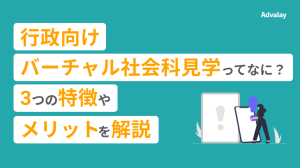
⑥バリアフリーツーリズムの推進
オンラインツアーは、身体的制約により観光が難しかった方々にも旅行体験を提供できる重要なツールです。車椅子での移動が困難な歴史的建造物や、アクセスが難しい離島や山岳地帯など、物理的バリアがある場所でもオンラインであれば誰もが平等に訪れることができます。
福祉施設や高齢者施設でのレクリエーション活動としても活用されており、施設にいながらにして旅行体験を楽しむことで、精神的な健康増進や認知症予防にも効果が期待されています。
⑦災害復興・文化財保存の記録
Matterportによるオンラインツアーは、災害リスクがある文化財や歴史的建造物のデジタル保存としても重要な役割を果たします。2019年に火災で大きな被害を受けたフランスのノートルダム大聖堂は、幸いにも火災前にMatterportで記録されていたため、復元作業の貴重な参考資料として活用されました。
日本でも、熊本城や首里城など、地震や火災で被害を受けた文化財のデジタルアーカイブ化が進められています。万が一の災害時にも、その文化的価値を後世に伝えるためのバックアップとして、また復元のための正確な記録として、Matterportによるデジタル保存の重要性は高まっています。
オンラインツアーを導入するメリット
オンラインツアーを導入するメリットは次の4つです。
- 世界中に施設をPRできる
- コスト削減になる
- いつでも自由に観光できる
- データ分析による来訪者の行動把握
世界中に施設をPRできる
Matterportのオンラインツアーは、ホームページやSNSに自由に掲載できるため、世界中のユーザーがアクセスできます。
文章や画像では伝わりきらない施設の臨場感や世界観を表現できることで、国境を超えて注目を集められるのではないでしょうか。
特に世界遺産や日本ならではの施設は一度データを制作しておけば、半永久的に保管できるため建物が倒壊したとしても、その魅力を発信し続けられるのものメリットといえます。
また、Matterportはもともとアメリカ発祥の技術であるため、海外のユーザーにも受け入れられやすいコンテンツです。
世界中の観光客に対して母国語で情報発信できる点も大きな強みです。Matterportのタグ機能を活用して多言語対応のコンテンツを埋め込むことで、言語の壁を超えたプロモーションが可能になります。特にインバウンド観光に力を入れている自治体や施設にとって、訪日前の外国人観光客への効果的なアプローチ手段となります。
実際に京都の寺院や東京の浅草などの観光地では、英語、中国語、韓国語、フランス語など複数言語に対応したMatterportツアーを公開し、訪日前の外国人観光客の関心を高めることに成功しています。多言語対応のガイド不足という課題をデジタル技術で補完することで、より多くの外国人観光客を魅了する取り組みが進んでいます。
コスト削減になる
オンラインツアーを行うことはさまざまな場面においてコストの削減につながります。
オンラインツアーに参加するユーザーは、移動にかかる費用や時間を削減できるため、より手軽に観光を楽しめるようになります。さらに施設や企業側も案内にかかる人件費や移動コストを削減できるため、コスパよくツアーを実施できます。
さまざまな企業でDX化が進んでいるように、デジタル技術を上手く活用することでビジネスモデルをまるごと改善でき売上アプにもつながるのではないでしょうか。
いつでも自由に観光できる
オンラインツアーは24時間365日閲覧できるため、時間にとらわれず自分の好きなタイミングで観光できます。
さらに現地に訪問するには、体力面や費用面、天候などさまざまな制約が発生しますが、オンラインツアーではMatterportを表示するデバイスとネット環境さえあればだれでも参加可能です。
「仕事で時間がないけど、一度は〇〇に行ってみたい」「年をとってしまい、体力的に旅行は難しい」など、今まで観光を諦めてしまっていた人にもオンラインツアーの魅力は大きいのではないでしょうか。
ウィズコロナの新しい観光スタイルとして、デジタルとリアルを融合させたオンラインツアーは今後多くのシーンで活用されることが予想されます。
時間的・地理的制約を解消するメリットは、特に以下のようなケースで効果を発揮します:
- 遠隔地の名所へのアクセス: 例えば日本の地方在住者が海外の有名美術館を訪問したり、逆に海外在住者が日本の離島の風景を楽しんだりすることが可能になります。
- 季節限定の風景体験: 桜の満開時期や紅葉の見頃など、限られた期間しか見られない景色を、いつでも最高の状態で鑑賞できます。
- 混雑回避: 人気観光地の混雑を避け、ゆっくりと展示物を鑑賞することができます。
- 閉館後や休業日のアクセス: 美術館の閉館後や休業日でも、作品を鑑賞することができます。
実際のユーザーデータによると、オンラインツアーの利用時間帯は夜間(20時〜24時)が最も多く、次いで早朝(5時〜7時)という結果が出ています。これは、通常の観光施設が営業していない時間帯に、仕事や家事の合間を縫って「ちょっとした旅行気分」を楽しむ人が多いことを示しています。
4. データ分析による来訪者の行動把握
<span style=”color:red”>Matterportを活用したオンラインツアーでは、ユーザーの閲覧行動をデータとして収集・分析することができます。どの展示に最も時間を費やしているか、どのルートで施設内を移動することが多いか、どの情報タグがよく閲覧されているかなど、詳細な行動データを取得できます。
このデータを分析することで、実際の施設運営やマーケティング戦略に活かすことが可能です。例えば:
- 人気展示の把握: 最も注目されている展示や空間を特定し、実際の展示レイアウトの参考にする
- 動線の最適化: ユーザーの動きやすいルートを分析し、実際の施設の案内サインや配置を改善する
- コンテンツ改善: 閲覧率の低いコンテンツを特定し、より魅力的な情報提供方法を検討する
- ターゲット分析: 訪問者の地域や閲覧時間帯などの統計から、効果的なプロモーション戦略を立案する
あるテーマパークでは、オンラインツアーの閲覧データを分析した結果、予想外のアトラクションに関心が高いことが判明し、そのアトラクションのプロモーションを強化することで、実際の来場者数の増加につながった事例もあります
オンラインツアーの作り方
オンラインツアーは次の手順で制作します。
- 打ち合わせ
- 撮影
- 編集
- 納品
打ち合わせ後は、ほぼ丸投げでオンラインツアーのデータが完成するので、専門知識がない方でも簡単にツアーを実施できます。
打ち合わせ
撮影の日程や、撮影できない場所など、プランナーと打ち合わせを行います。
撮影
撮影日当日は、まずカメラマンと一緒に現地確認をしていただきます。その後は、カメラマンのみで撮影を進行するため、立ち会いは不要です。
基本的にカメラマン1〜2名で撮影を行います。
観光地など人通りが多い施設は、休館日や朝方を狙って撮影を行います。
編集
撮影が終了したら、生成された3Dモデルを編集します。
施設や展示物の説明テキストや動画の埋め込みを中心に、充実したコンテンツになるようデータを仕上げます。
納品
編集まですべて完了したデータは、発行されたURLで納品します。
データの活用方法や集客方法についてもご相談に乗れますのでお気軽にお問い合わせください。
またオンラインツアーの作り方については、バーチャル美術館の事例を取り上げ、下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。
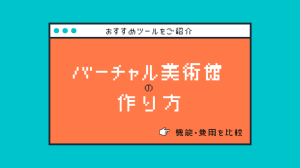
最後に
オンラインツアーは、リアルとデジタルを融合した新しい旅行スタイルを実現した画期的なサービスです。
観光の分野はコロナ禍で特に大きな影響を受けた業界で、多くの企業に被害が発生しています。
このような状況下だからこそ、新しい旅行の可能性を拡張し、一緒に観光業界を盛り上げることができれば幸いです。
オンラインツアーについてのご相談はぜひお気軽にお問い合わせください。