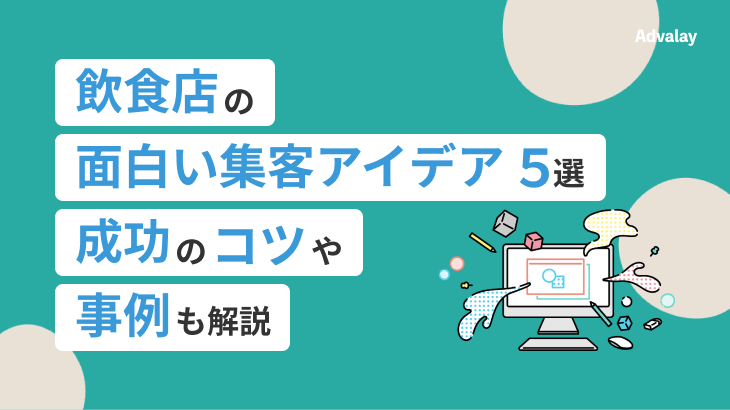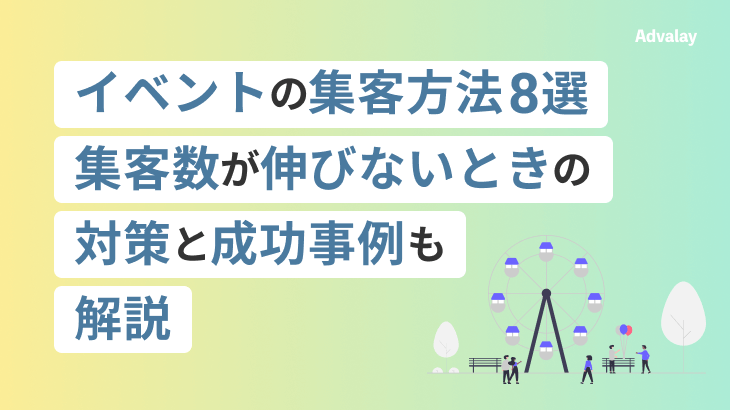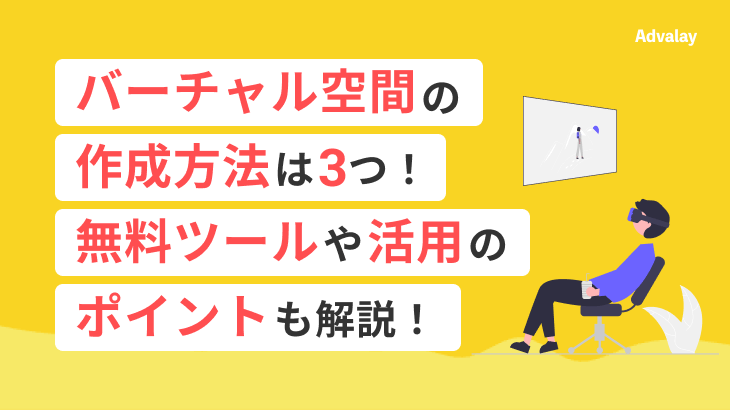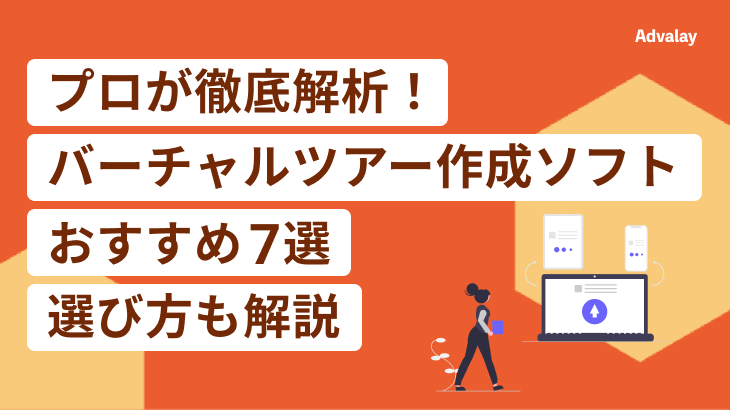AIで建築パースは作れる?メリット・デメリットと具体的な方法を解説
建築パースとは、建築物の完成イメージを視覚的に表現するための3Dレンダリングやイラストのことを指します。従来、建築パースはCGデザイナーや建築設計者が専門ソフトを使用して制作していました。
しかし、近年のAI技術の発展により、AIを活用した建築パース制作が注目を集めています。AIを活用すれば、短時間でリアルな建築パースを生成できる可能性があり、建築業界の業務効率化につながると期待されています。
一方で、AIによるパース生成にはいくつかの課題も存在するのが事実です。
そこで本記事では、AIで建築パースを作る方法やメリット・デメリット、そして注意点について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
AIで建築パースは作れるのか?
結論、AIで建築パースは作ることは可能です。ただし、初期段階のアイデア出しや概念の視覚化など用途は限定的です。
専門的な設計図や詳細な建築プランといった細かい作業まで完結できるわけではありません。現状、以下のような方法でAIを活用した建築パースの生成が実用化されつつあります。
- コンセプトデザインの作成:初期のアイデアスケッチをAIに入力し、ビジュアルを生成
- クイックプレビュー:建築デザインの大まかなイメージをAIで作成し、クライアントへの提案時に活用
- 3Dモデルからの画像生成:BIMソフトや3DモデリングソフトとAIを組み合わせてレンダリングを効率化
AI技術は急速に進化しており、画像生成分野でも大きな成果を上げています。特に「ディープラーニング」を活用した画像生成AIは、写真のようにリアルなイメージを短時間で作成できるようになりました。
AIによる建築パース制作は、以下のような場面で特に有効です。
- アイデア段階のビジュアル化
- コストや時間を削減したデザイン検討
- 多様なデザインパターンの自動生成
ただし、AIはまだ建築の専門知識を持っているわけではないため、精密な設計や構造の正確性を求める場面では人の手による修正が不可欠です。
AIで建築パースを作る具体的な方法
AIで建築パースを作る方法には、主に画像生成AI、3DモデリングAI、レンダリングAIを活用する方法があります。まず、画像生成AI(例:Stable Diffusion、DALL·E)を使用すると、テキスト入力や参考画像から建築パース風のビジュアルを自動生成できます。
次に、3DモデリングAI(例:SketchUpのAIプラグインやNVIDIA Omniverse)を利用すると、間取りや外観デザインのモデリングを短時間で作成できます。
さらに、レンダリングAI(例:Lumion AI、Enscape)を用いれば、リアルなライティングや素材感を自動調整し、高品質なパースに仕上げることが可能です。
特に、複数のAIツールを組み合わせることで、効率よく高精度な建築パースを制作できるのが大きな魅力です。
AIを活用した建築パースのメリット
ここからは、AIを活用した建築パースのメリットを4つにまとめて紹介します。
作業時間の短縮
AIを活用することで、建築パースの作成時間を大幅に短縮できます。従来のパース制作では、設計者が3Dモデリングを行い、レンダリングや細かな調整を繰り返すため、多くの時間がかかりました。
しかし、AI画像生成ツールや自動レンダリング技術を活用すれば、数秒から数分でビジュアルを生成できます。また、AIは学習したデータを基に最適な構図やライティングを自動調整するため、手作業で試行錯誤する必要が減り、修正作業の負担も軽減可能です。
これにより、設計者は本来の業務に集中でき、短期間で複数のデザイン案を作成できます。特にプレゼンテーションやクライアントとの打ち合わせの際、スピーディーなビジュアル提示が求められる場面では、AIの導入が大きな強みとなります。
コスト削減
AIによる建築パース作成は、コスト削減の面でも大きなメリットがあります。通常、建築パースの作成には専門のCGデザイナーに依頼する必要があり、外注費用が発生します。
特に高品質な3Dモデリングを求める場合、数十万円の費用がかかることも珍しくありません。しかし、AIツールを活用すれば、低コストでパースを自動生成でき、外注費や人件費を抑えることが可能です。
さらに、AIは一度導入すれば繰り返し使用できるため、長期的に見てもコストパフォーマンスに優れています。
初期段階のデザイン案を作成する際や、クライアントに複数案を提示する場面では、AIを活用することで予算を抑えながら高品質なビジュアルを提供できるのが魅力です。
アイデア出しがスムーズ
建築デザインの初期段階では、アイデアを具体化するプロセスが重要です。AIを活用することで、スケッチや手描きのラフイメージをもとに、瞬時にパース化したビジュアルを生成できます。
例えば、テキストプロンプトを入力するだけでAIが建築デザインの提案を行うツールもあり、イメージを素早く形にすることが可能です。
また、AIは過去のデータを学習し、トレンドを反映したデザインや新しいスタイルの提案も行えるため、設計者のインスピレーションを刺激する効果も期待できます。
多様なバリエーションを短時間で作成できることから、クライアントとの意見交換がスムーズになり、デザインの方向性を早期に確定しやすくなるのが大きなメリットです。
手軽に高品質なビジュアルを作成
従来の建築パースは、専門的な3Dソフトやレンダリング技術が必要であり、扱うには高度なスキルが求められました。しかし、AIを活用すれば、誰でも手軽に高品質な建築パースを作成できるようになります。
例えば、AI搭載の3Dレンダリングツールでは、ワンクリックでリアルなライティングや素材感を調整でき、プロのデザイナーが手掛けたようなビジュアルを簡単に出力できます。
また、AIの画像補正機能を活用すれば、既存のパースをよりリアルに加工することも可能です。これにより、設計者や営業担当者が、デザインの知識がなくても短時間で魅力的なプレゼン資料を作成できるという大きな利点があります。
AIで建築パースを作るデメリット
続いて、AIで建築パースを作るデメリットを3つにまとめて紹介します。
デザインの自由度が低い
AIを活用して建築パースを作成する場合、デザインの自由度が制限されることがあります。多くのAIツールは既存のデータセットをもとに画像を生成します。
そのため、ユーザーが細かい指示を出したとしても、独自性の高いデザインを完全に再現するのが難しいのです。例えば、特定の建築スタイルや素材感、照明条件などを詳細に設定したい場合、AIでは理想の結果が得られないこともあります。
また、過去のデータをもとに生成するため、斬新なデザインや新しいコンセプトの建築パースには不向きな場合があります。
特に、完全にオリジナルの建築デザインを求めるプロジェクトでは、AIが生成するビジュアルでは満足できず、最終的に手作業で調整する必要が生じるでしょう。
そのため、AIで作成したパースを最終デザインとして採用するのではなく、あくまで初期のアイデア出しやプレゼン用のイメージ作成として活用するのが現実的な使い方となります。
細かい調整が難しい
AIによる建築パース作成では、細かいディテールの調整が難しいという課題があります。例えば、窓やドアの位置、屋根の傾斜角度、外壁の素材感など、設計者が細かくこだわりたいポイントをAIが完全に反映するのは容易ではありません。
現在のAI技術では、大まかなデザインや雰囲気は再現できても、細部の精度を求めるには限界があるのが実情です。
また、生成されたパースの一部を修正したい場合も、AIが自動的に全体のバランスを調整してしまうため、ピンポイントで特定の部分だけを変更するのが難しいことがあります。
例えば、「窓枠のデザインを変更したい」「植栽の配置を少しずらしたい」といった微調整を行うには、AIツールの編集機能では不十分であり、結局は手作業で修正を加える必要が出てくることもあります。
AIを活用する際は、最終的なクオリティを向上させるために、人間の手による仕上げ作業が必要になることを前提にしておくべきでしょう。
建築基準や構造的な正確性に欠ける
AIで生成された建築パースは、見た目の美しさを重視する一方で、建築基準や構造的な正確性が考慮されていないことが多い点に注意が必要です。
例えば、現実の建築設計では、耐震基準や建築基準法に則った構造設計が求められます。しかし、AIはそれらを考慮せずにビジュアル的に魅力的なデザインを優先して生成します。
また、AIが生成する建築パースには、実際には施工が難しいデザインが含まれることもあり、実用性に欠けるケースがあるのも問題です。たとえば、柱の配置が不適切だったり、実際には使用できない素材がレンダリングされていたりすることもあります。
そのため、AIが作成したパースをそのまま実際の建築設計に落とし込むことは危険であり、専門家によるチェックが不可欠です。
このような理由から、AIによる建築パースはあくまでコンセプトデザインやプレゼン用のビジュアル作成に限定し、実際の設計には専門家の知識と経験を活かして最終調整を行うことが重要です。
AIで建築パースを作る際の注意点
ここでは、AIで建築パースを作る際の注意点を3つにまとめて紹介します。
最終的な調整は人間が行う
AIで建築パースを作成する際は、最終的な調整を必ず人間が行うことが重要です。AIは短時間で魅力的なビジュアルを生成できますが、細かいディテールや意図したデザインを完全に反映するのは難しい場合があります。
例えば、素材の質感や光の表現、建物の細部にこだわるといったクリエイティブな要素は、設計者やデザイナーが手作業で仕上げる必要があります。
また、AIが生成するパースには、実際の建築設計には適さないデザインが含まれることが少なくありません。そのため、バランスや構造的な整合性を考慮した微調整も求められます。
AIはあくまで「たたき台」として活用し、最終的な仕上げは専門家の手で行うという姿勢が欠かせません。
建築基準や構造のチェックが必要
AIが生成する建築パースは、見た目の美しさを優先するため、建築基準法や構造的な要件を満たしていないことがあります。例えば、日本の耐震基準に適合しない柱の配置や、建築基準法に反する高さ・建ぺい率のデザインが含まれることなどです。
そのため、実際の設計に落とし込む際は慎重なチェックが必要です。特に、商業施設や公共建築物など、厳しい基準を求められる建築物では注意しましょう。
構造計算や法規制の確認を行わずにAIのデザインを採用すると、後の設計変更や修正に大きな手間がかかる可能性があります。AIによるパースを活用する際は、建築士や構造設計者と連携しながら、適切な修正を加える工程を設けることが重要です。
AIの著作権・商用利用制限に注意
AIで生成した建築パースを商用利用する際は、著作権や利用規約を事前に確認しましょう。多くのAIツールは、生成された画像の使用権をユーザーに提供しますが、一部のサービスでは著作権がAI提供元に帰属するケースもあります。
そのため、クライアント向けの提案資料や広告などで利用する場合は、利用規約を十分に確認し、問題がないかをチェックすることが重要です。
また、生成された画像が他のデザインと類似する可能性もあるため、完全オリジナルのデザインを求める場合には注意が必要です。万が一、他者の著作物と似たデザインが生成されてしまうと、著作権侵害のリスクが生じる可能性もあります。
そのため、最終的なデザインの確認と必要に応じた修正を怠らないようにしましょう。
建築パース外注におすすめの業者
最後に、建築パース制作を依頼できるおすすめの外注先を紹介します。日本国内で実績豊富な会社と、低コストで依頼可能なコスパ重視の会社をピックアップしました。
自社のニーズに合った業者選定の参考にしてください。
株式会社Advalay

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社Advalay |
| 所在地 | 〒106-0031 東京都港区西麻布4-10-16ウエストコート410 2F |
| 公式HP | https://www.advalay.co.jp/ |
Advalayは、日本を代表する建築CGパース制作会社の一つです。最新の3DCG技術と熟練のクリエイターチームによって、高精細かつリアルなパースを短納期で提供できる点が強みです。
特に、大規模建築や複雑な構造物の表現に優れ、大手デベロッパーや有名設計事務所からの多数の受注実績を誇ります。さらに、建築CGにとどまらず、VR・AR、メタバース空間での建築プレゼンテーションにも対応しており、先端技術を活用した提案力にも定評があります。
価格帯は中〜高価格帯が中心で、広告代理店経由の大型案件やハイクオリティを求めるプロジェクトで選ばれることが多いです。クオリティ・技術力・対応力のすべてにおいてトップクラスの実力を誇る企業です。
パース工房

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | パース工房 |
| 所在地 | 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田1丁目10-59 |
| 公式HP | https://pers-koubou.com/ |
パース工房は、静岡県に拠点を置く建築パース専門会社で、低価格かつ迅速なサービスを提供しているのが特徴です。初回依頼時には10%OFFの割引が適用されるため、コストを重視する顧客に人気があります。
料金設定は業界内でも非常にリーズナブルで、戸建住宅や集合住宅の内観・外観パースが各27,500円(税込)〜と手頃な価格で依頼可能です。ただし、この価格はCADデータの支給が前提となっており、図面がない場合や複雑な案件では追加費用が発生します。
対応範囲は、戸建住宅・マンション・オフィス・商業施設など多岐にわたり、手描き風パースや簡易鳥瞰図の制作にも対応。納期も比較的短く、小規模案件なら約1週間で納品可能なスピード感も魅力です。
「コストを抑えたい」「簡易なパースが必要」といったニーズに適した会社といえるでしょう。
まとめ
AIを活用すれば、建築パース制作のスピードやコストを大幅に削減できます。しかし、現時点では細部の調整や建築基準への適合といった課題が残っています。
そのため、AIと従来の手法を組み合わせたハイブリッドな活用が理想的です。今後、AI技術がさらに進化すれば、建築パース制作の新たなスタンダードとなる可能性もあります。
定期的に最新情報をチェックするようにしましょう。本記事があなたのお役に立てることを願っております。